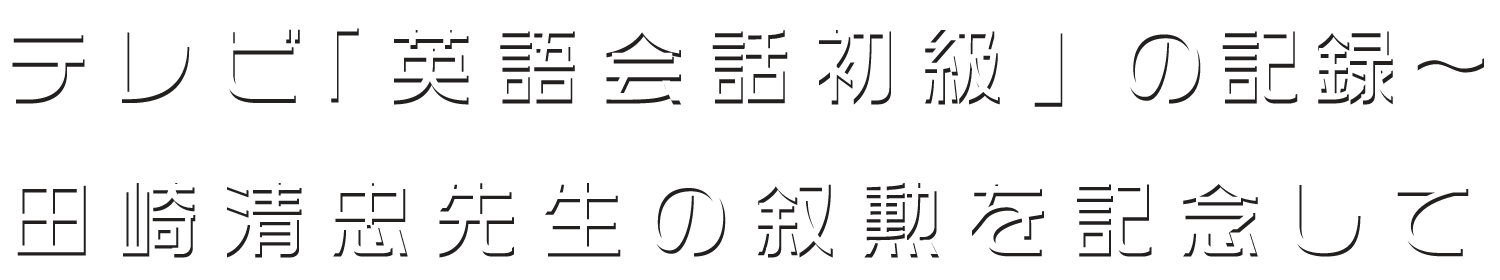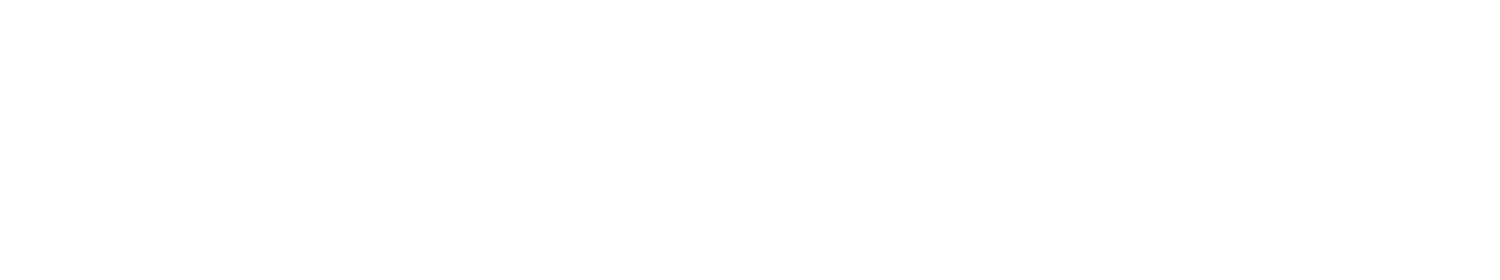「英語会話初級」を支えたその時代
宇佐美昇三さん(昭和39年~49年、英語会話班PD、その後、文研主任研究員)

昭和40年、スタジオで 「The Lost Bag」のFDを務める宇佐美さん
| ちょうどオリンピック東京大会が、1964年夏、東京で開かれたとき、通新教育部の語学班からは何人かディレクターが放送センターに臨時出向し、各国のスポーツ番組制作を支援していた。 宇佐美はその夏、国際局報道部から念願の教育局に転勤し、通信教育部語学班に配置された。入局前は学校放送のシナリオを書いたり、国際局では短波の海外向けラジオ番組を制作していたが、国内向けのラジオ、テレビ番組の担当は初めてである。田崎先生は既に「英語会話初級」でスキットを使い、提示、説明、練習、定着の各段階を踏まえた番組フォーマットを完成しておられた。年間シラバスがあり、狙いは英語で表現する力をつけることである。担当は長岡熙、土屋二彦、田中卓で月、水、金の放送であった。 「英語会話中級」は水谷雄二郎、大石卓志に小生が見習いで参加、火、木曜日の放送であった。こちらはウイリアム・ムーア先生で、リスニング力の養成をうたい、様々な物語や対談を30分番組内で2回繰り返し、中間に日本人アシスタントの解説を入れた。特に階段型のシラバスはなく、いわば学習者が英語の尾根に挑戦して聞き取り登るというやり方である。 1965年3月、それまでの学習の総仕上げとして初級と中級が合同して3本連続の番組を作ることになり、30分×3本=計90分の英語ドラマで、初級で扱った表現を入れつつ、解説もあり、やや長いリスニング部分もある「The Lost Bag」が企画された。 「英語会話初級」の言語教材には、様々なものがある。「路上にて」(”Hello!“,”Hi!”といった挨拶)から始まって、「空港にて」(入国管理官、検疫官、税関吏とのやりとり)、「タクシーにて」(ホテルへ)、「ホテルにて」(チェックイン、部屋でボーイにチップ)、「レストランにて」(食事や飲み物の注文)といった俗称「~~にて」ものが定番で、これをつなげば「アメリカ旅行物語」は出来るが、面白くはない。そこで劇では「カバンを紛失する」事故を発生させて視聴者に次回への興味を抱いてもらえるようにした。しかし、限られた初級の英語表現だけではドラマに必要な科白を揃えられない。どうしても難しい中級の表現が出る。そこで中級の表現がでたら、田崎先生に「こういう意味です」など解説をお願いすることになった。 初級の表現にしても、視聴者は4月からの教材をすべて習得しているわけではない。和訳や発音練習なども盛り込みたい。しかし、劇中で、視聴者に急に「さあ練習してください」では流れが消える。そこで田崎先生の旅行同伴者をアメリカが初めての英語学習者にすれば、その人が視聴者の分身になる。なるべくならプロの俳優をお願いすれば、ドラマとして見栄えが向上すると決まった。そのころ芸能局では末盛憲彦、林叡作、両ディレクターが「夢で会いましょう」という楽しいバラエティ番組を制作・放送していた。渥美清、E.H.エリック、坂本九、永六輔、三木のり平などの芸達者に伍して黒柳徹子さんがレギュラーだった。NHK放送劇団所属の黒柳さんに、田崎先生の奥様役をお願いすれば面白くなりそうだと、長岡さん(だったとおもう)が出演交渉すると、彼女も英語に興味があるということで話しがまとまった。 田崎先生が奥様役の黒柳徹子さんを伴って米国旅行に行く。その飛行機に乗り合わせたのがムーア先生と息子である。着陸したとき黒柳さんのものとムーアさんのボストンバッグが間違って入れ替わってしまう。しかし、それが縁でムーア家のパーティに招かれて、アメリカ生活を楽しむのだった。 もう一つ教育番組としてドラマ仕立ての問題点は、文字をどうするかだった。英語を音だけで聞かせる試みは、のちの初級シリーズでは試みられたが、当時はまだそこまで踏み切れなかった。それまで散々テロップやフラシュカードで文字を見せてきている。そこで黒柳さんが、新しい英語表現を覚えるために道中日記にそれらを書き留めることにした。当時のテレビカメラは4本ターレットのついたビール箱くらいの代物で、畳半畳くらいのドリーという台車に乗っている。今よりはるかに機動性が乏しい。ドラマ本番中に黒柳さんの肩越しに道中日記の紙面アップなど到底撮影できないので、「吹き替え」の道中日記を作業机の上に置き、美術センターからタイトルの書き手に来てもらって、その書く手元だけを撮影した。このため3台使えるカメラのうちの1台はドラマを撮ったり、道中日記を撮ったりと忙しいことであった。 黒柳さんは、例えば「何かを下さい」という英語は”~~please.”と習うと、すぐ道中日記に書き留める。それを暗記するために口ずさむ、夫役の田崎先生が、にこやかに発音を修正してあげる。自信を得た黒柳さんが、早速、レストランで「パインジュース、プリーズ」と注文すると、ボーイに通じない。「パイナップルジュース」といいなさいと田崎先生が教える。こうして教育番組に仕立てた。 アメリカ人たちは素人でも概して芸達者だった。しかし、場面ごとに多数の米人をお願いするのは予算も演出陣の作業量もパンクするので学校放送に出ていたトム・キローさんに税関吏、レストランのウエイター、運転手など7つの役を次々に演じてもらった。キローさんが違う役で出る毎に黒柳さんが「マーどこかで会ったわ」などとアドリブを入れ、おかしみを加えた。 田崎先生の金曜日シリーズは、場面別の表現でなく、「…を頼む」「…を希望する」という今で言うノーショナル、ファンクショナル・シラバスを採用していた。また場面別も毎年、状況を変えて田崎先生扮する一家がアメリカに移住するシリーズは、翌年はアメリカ人が日本に来て、田崎家と交流するように変えられた。それにしたがって簡単な場面別表現であっても、違う語彙、文型が導入され、「毎年継続して視聴すれば使える英語表現が豊かになる」という仕組みだった。田崎先生はあくまでも英語の勉強であり、「英語会話」で「英会話」ではないと折にふれて語られた。 学習心理学の面からは「刺激―反応理論」が基礎のミシガン派の反復練習を留学時代に習得されて背骨とされたとお見受けした。しかし、それを墨守することなく、テレビという新しい視聴覚教育手段の特性を生かされた。例えば画面を4分割して選択肢(アイスクリーム、コーラ、ジュース、コーヒー)を配置し、それをランダムに提示することで素早く視聴者に発話させる練習や、数人のネーティブを階段上に並べて同じ表現でも違う人が発声させることで、音調や表情が違うことを示し、反復練習が退屈な機械的なものにならないように配慮された。 若いディレクターたちが新鮮な演出アイデアを持ち込むと、それを英語教育の立場から間違いのないものに修正して活用された。その柔軟さは見事だった。 オリンピック東京大会で海外からお客様をお迎えする時代から、日本経済の高度成長により、商社や外交官だけでなく、誰でもが国外に出かけてゆく段階を迎えた。一方、あれほど盛んに見えたアメリカがベトナムでの失政や、内政のゆがみで翳りをみせ、英語もネーティブ中心のものから非英語国民間の共通語としての重みを増やし始めた。かつては珍しかった高速道路やハンバーガーが日本でも普及し、それらをテレビで提示して語彙や表現を増やさなくても外国で戸惑う日本人は減り始めた。 しかし、1ドルがまだ実質400円のころ、田崎先生が自費で毎年アメリカに録音機とカメラを持参して教材を収集され、それらを番組に反映してくださったご努力は敬服に値する。星条旗は今日、少し勢いがないが、1970年まではまだ、高く靡いていたから。 |