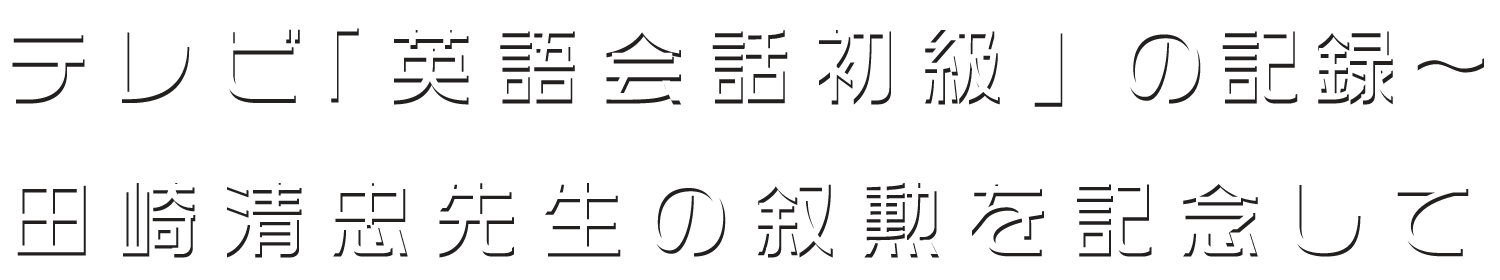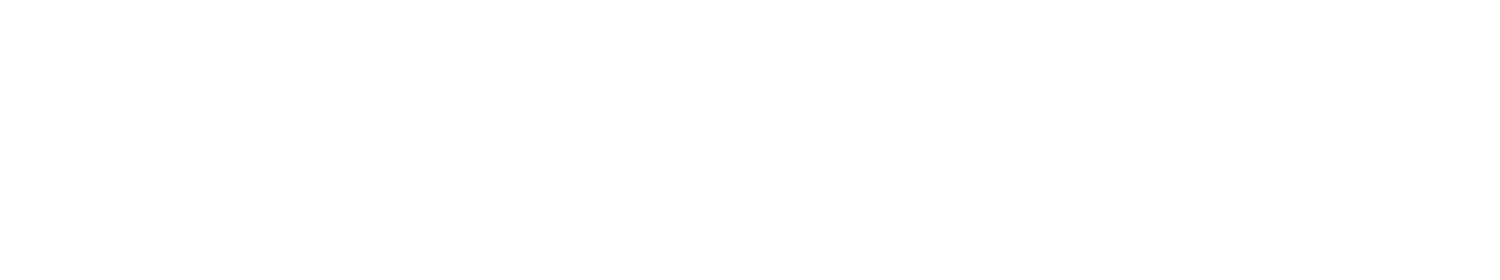番組作りの醍醐味を教えてもらった
小河原正己さん(昭和43~46年、「英語会話初級」PD)

昭和43年スタジオにて、田崎先生と(中央)鷲津名都江さん
| 私が、テレビ「英語会話初級」を担当したのは、NHKに入って4年目のことだった。やる気だけはあるのだけれど、ちょっとクサッていた時期だった。というのは、NHKに入局した昭和39年、新人として初めて内示された配属先が、全く予想もしなかった国際局だったからである。 当初は、「いきなり海外特派員!」と大いなる勘違いを(?)したのだが、それは、外信部の仕事。国際局とは、短波を使って、世界に向けてラジオ・ジャパンを放送しているセクションである。自分はテレビをやりたくて、NHKに入ってきたのに、テレビはない(時代は変わって、現在は、テレビ・ジャパンというテレビ放送を世界に向けて発信している)。それに、何より、外国語が不得手で、自分が最も敬遠したい部局だったのである。 それから、なんとか希望がかない、1年で国際局を抜け出して、念願の番組制作局に異動した。しかし、そこで出会ったのは、再び語学だったのである。局の人事担当者としては至極当然の措置だったのだろう。「国際局から来たのなら、語学は大丈夫だろう。本人は『全く駄目』と言っているようだが、何とかなるだろう」「いえ、いえ、それが何ともなりません、『からっきしダメ』なのです!」 通信教育部の語学班で、最初に担当したのは、「たのしいフランス語」だったが、やっぱり「からっきしダメ」だった。最初の番組担当で、先輩から渡されたのが、前週の残り台本とハサミ、のり、そしてテキストのゲラ(当時のコピーは、まだ青焼き)だった。つまり、テキストのゲラを切り刻んで、台本に貼り付け、もう一つのゲラのコピーを切って、テロップとパターンの原稿用紙に貼り付けると、ほとんど番組の準備は出来上がりとなる。講師の先生方やフランス人ゲスト、先輩諸氏との付き合いは極めて楽しかったが、でも、これは自分が考えていたテレビではないな、と思った。 またまた別の部に、というか、もともとの希望の部に、異動願いを出してもかなうわけがないのは分かっていたので、上司に、隣の班への異動を頼み込んだ。それが「英語会話初級」の班だった。前から、隣の連中が何かイキイキと仕事をしているのが伝わって来ていたからだ。昭和43年のことだった。 すぐには、「初級」のPDはさせてもらえず、最初の担当は、ラジオの英語番組だった。新たに講師を迎えるから、担当者も新しくしようということで、「お前やれ」と、私にお鉢が回ってきたのである。すでに、新しい講師は、テキストの執筆に入っている段階で、作業は順調に進んでいる……はずであった。ところが、その翌日、テキストの編集者から連絡が入った。 「大変です、先生が、原稿が書けないのです」 あわてて、先生のマンションに駆けつけ、結局それから2晩泊り込みになったのである。スキットが作れないのだ。確かに、番組の講師になったばかりの先生方にとっては、テレビやラジオのスキット作りは初めてのことで、皆さん苦労される。しかし、スキットができなければ、教材が作れない、つまりはテキストができない、テキストができなければ番組が作れない、というのはテキスト番組の宿命である。となると、番組担当者が、つまり、私が、スキットを作るしかない。もちろん英語はできないから、日本語で書いて、先生が英語に直し、それを基に教材を作る、という流れ作業である。これが、翌月、翌々月と繰り返されることになったが、担当者としては困ったことになったと思う反面、後述するが、自分にとっては願ってもないことだったのである。いずれにしても、おかげでスキットを作ることの難しさと楽しさを知ることができ、それが「英語会話」番組の初仕事となったのである。 その後、テレビ「英語会話初級」のPDを担当することになるのだが、その経験があったことで、田崎先生のスキットの素晴らしさを、多分誰よりもよく知ることができたのである。 (なお、英語会話番組の中で演じられる寸劇を、スキットと呼ぶようになったのは、田崎先生が最初だったということを最近知った。もともとは、心理学の中で使われるロール・プレー劇を指す用語だったという) 番組を担当してしばらくすると、田崎先生が作るスキットやテキストの中に、宝物と言ってもいいような情報が、あちこちに書き込まれていることに気づかされることになる。 言うまでもなく、「英語会話」のスキットの基本は、会話そのものと、話される場面によって構成される。つまり、「あいさつ」とか「紹介」の仕方などの言い回しと、「公園にて」とか、「駅で」「銀行で」などの場面設定で、初級英語会話の場合、それらは、ある部分定型化し、講師の先生や年度が変わっても、そのパターンはあまり変わりようがない。 しかし田崎先生のスキットには、短く、定型化された中でも、そのたびに新しい情報や生きたノウハウが入っているのである。 それは、先生が、番組が始まると毎年夏休みに、自腹で、アメリカまで取材旅行に行かれるその成果が盛り込まれていたからである。スキットとそれに付された解説は、その時代のアメリカの人々の暮らしや仕事がふんだんに取り込まれたアメリカ見聞録になっていたのである。 番組が終わるまでに、先生の取材旅行は、50州すべてに及ぶことになるが、その結果、テキストには、今考えると、ビジネス・チャンスにつながる事業や商売のタネがいくつも埋め込まれていたのである。 今でもはっきり覚えていることがある。その日のレッスンのテーマは、「商店にて」だった。どの英語会話教材にも出てくる場面設定である。ところが、この「商店」は、それらの教材に出てくる、一般的な店ではなかった。 それは、「コンビニエンス・ストア」(テキストは、コンビニエンス・マーケットだったかも、、、)と呼ばれる店、つまり「便利な店」とか、「便利屋」と呼び、当時では珍しく、朝7時から夜11時までやっているというのである。 そして、店の名前が「7-Eleven」(今のマークと同じ看板がかかった店の写真も紹介されていた)。つまり、今や日本でも隆盛を極めている「コンビニ」であり、「セブン・イレブン」なのである。今では、24時間営業の店も多いが、当時は、普通、朝10時頃から夕方5時~6時までしかやっていない商店が多い中で、早朝7時から深夜11時まで店が開いているなどとは考えられなかった時代である。それだけに、「便利店」、「7-11」というコンセプトは画期的なもので、そのコンセプトをそのまま名前にした命名そのものにも驚かされた。さすがアメリカと思ったものだった。その時、日本にも、こんな店ができたら「便利」なのになあ、いや、きっと日本にもできるだろう、と思ったものである。それが、昭和44年か、45年のことだった。 それから4~5年後、日本にも登場するのである。イトーヨーカ堂との提携により、日本で初めてのコンビニエンス・ストア「セブン・イレブン」が登場したのが、昭和49年だった。そして、同社のHPによると、現在「7-Eleven」は、買収により、全面的に日本の会社となっているという。40年前に、田崎先生が、デンスケを抱えて、アメリカで取材したあの店が、である。 もしかしたら、イトーヨーカ堂の社長が、「初級」のファンだったのかも…… その他、解説には、「7-Eleven」という店以外にも、「7-Twelve」という店もあるとあったが、後者は、さらに1時間長く店を開けていたのに、何故かその後消えてしまう。店名の語呂の良さが(キャッチフレーズが「セブン・イレブン、いいキブン」、アメリカでは、「Thanks Heaven, Seven Eleven」)、生き残りのポイントだったのではと愚考するが、そんな面白い話が、テキストの中にちりばめられていたのである。 そんなスキット作りの名手、田崎先生から、ある時、長いスキットを書いてくれ、と頼まれたことがある。頼まれた、というより、自分から志願した、と言った方が正しいかもしれない。長いスキットとは、英語ドラマの台本作りのことである。 「英語会話初級」では、2、3年に1回、年度末に特集番組をやることになっていたのだが、今回は思い切って1時間のフィルム・ドラマを作って、それを教材に、3月の1ケ月間、日本文化を紹介するシリーズにしよう、ということになった。先生とスタッフで話し合って、「建築家森大作の案内で、アメリカの女性雑誌記者キャロリンが、東京と古都京都を訪ね、イキイキとした日本論を展開する」と、大雑把にコンセプトを決めた。 そして会議の席上、田崎先生は、「1時間もののドラマとなると、時間的にも、内容的にも、自分の手に負いかねるので、シナリオは、誰かPDさんが……」という。そこで、手を挙げたのである。何を隠そう、私、入局した当初の希望がドラマ部で、ドラマを作りたくて、NHKに入局したのだった。ところが、前述したように、最初の配属先が国際局、そして、そこを抜け出したと思ったら通信教育部ということで、その夢は脆くも挫折したのであった。ところが、田崎先生から、「ドラマのシナリオを」と持ちかけられて、一度は覚めた夢の世界に、引きもどされたのである。そして、無謀にも英語ドラマのシナリオ作りを引き受けたのである。(もちろん、言うまでもなく、書くのは日本語) 今でもそのシナリオを読み返すと、冷や汗が出てくるが、志とコンセプトだけは、稀有壮大だった。ドラマ・ディレクター志望であるからには、これまでにあるような、単純な日本紹介ドラマにはしたくない。そこで、当時建築中の日本一の高層ビル・京王プラザホテルと京都・東寺の五重塔を対比して、アメリカ人の目から見た日本文化論を展開しようということにしたのだが(高層ビルを設計する建築家・森大作建築事務所も、その当時は日本一高いビル、霞ヶ関ビルの1室という設定である) 東京の超高層ビルという近代技術と京都東寺の五重塔に象徴される日本の歴史文化という2本の竹馬に乗って歩む国ということで、当初のタイトルは、「竹馬に乗った日本」。なんとも力の入ったタイトルだ。 主役の美人女性記者を演じてくれたのが、Jane Fergusonさん。ハワイ大学で英語教育法を専攻、その学位を持って、来日、東京の大学で教鞭をとっていた。当時のハリウッド・スターで、ファースト・ネームが同じジェーン・フォンダ(恥ずかしながら、当時大ファンだった)似で、美しく、知性的な女性記者というドラマの主役を見事に演じきってくれた。極寒の京都ロケも綿入れをはおって乗り切り、田崎先生との呼吸もぴったり。これまで、外国人ゲストは、できるだけいろいろな発音を聞いてもらう、という田崎先生の方針で、短期間で交代してもらうことを原則としてきたが、この名コンビは、その翌年度も続いて、視聴者からの好評を得たのである。 さて、問題のシナリオだが、田崎先生が英語に書き換える段階で、肩に入っていた力を抜いてもらい、タイトルも、「thru carolyn’s eye」という、やさしくシンプルなものに変えてくれた。だが、タイトルなのに、すべて小文字である。教育番組の担当者として、私は、かくのごとく先生に申し上げた。「先生!tとcは、大文字ではないでしょうか?教育テレビなので、文法的に間違っているのは困ります。それに、thru は、throughの方がよくないでしょうか?」師、答えて曰く。「これでいいのです。これの方がおしゃれでしょう」さらに曰く。「英語のタイトルを、墨で筆書きするというのはどうですか」……(弟子、しばし無言)参った!確かにオシャレだ。先生のものを書き、ものを作るセンスの良さには、感嘆するばかりである。これを見ても、田崎先生は、名講師というだけでなく、ディレクターをうまく使い、堅苦しいタイトルを魅力的なものに仕立て直し、駄目な台本を見事な作品に仕上げる、名プロデューサーだったのが分かるのである。 それに、先生とジェーンさんの好演、今は亡き田中卓さんの演出により、お粗末なシナリオも、一応のレベルの英語ドラマに仕上がったのではある。当初は、この傑作ドラマのシナリオを持って、ドラマ部に乗り込み、一度は挫折したドラマ・ディレクターに返り咲いてやろうという(それまで一度も咲いてはいなかったが、そんな気分だった)、野心を隠し持っていたのだが、後にも先にも、ドラマ作りに関わったのはこの1本だけだから、その結果は明らかである。 次の私の失敗は、英語会話バラエティだった。 当時、アメリカで、子供向けの英語番組「セサミ・ストリート」が人気を呼び、民放では、巨泉、前武の「ゲバゲバ90分 」というテレビ・バラエティが当たっていた。わが「初級」でも、コント形式で、笑いながら、日本人が間違いやすい英語を提起し、正しい英語を身につけてもらおうというねらいの番組である。 先生とPDが、それぞれアイディアを持ち寄ろうということになったが、間違った英語も正しい英語も区別つかない私には、全く手が出ない。今思い出しても、電話のコントで「if、if、、、」程度しか出てこない。結局、英語コント作りは、私の手に負えず、結局番組の方も、日本人にとっては苦手な英語の発音を中心に、バラエティ風に紹介していくことになった。 その後、NHKスペシャル部で仕事をした時、大先輩たちが、見事なバラエティ向きの和製英語を使って番組評をしているのに舌を巻いたものだ。 Yディレクター曰く「放送が終わってからそんなことを言っても、after festivalだよ」 また、後輩たちから、先生と呼ばれていたY大ディレクター「こんな番組作って、nose high highになってたらno good」 言うまでもなく、「後の祭り」と「鼻高々」だが、「after festival」には、そこはかとない哀感が漂い、「nose high high」には、欧米人のように鼻を高くして、いかにも自慢げな英語に聞こえるから奇妙である。 私の、2年間の「英語会話初級」時代で、唯一番組に貢献したと自慢できるのは、「会話文型練習」シリーズである。 ある時、田崎先生から、「英語会話の練習法で、重要なものの1つに『substitution』がある。しかし、ラジオ、テレビは、これがなかなかうまくいかない。何か良い方法はないだろうか」と相談を受けた。いわゆる入れ替え練習で、基本的な文型の一部をいろいろに入れ替えて、様々な状況に応用するという練習である。 それまでは、ゲストがカメラ向きに、まずは基本文型を発音し、入れ替え用の言葉や文章を言った後、ポーズをとって、手のアクションなどで、視聴者に発話を促がすやり方が多かった。と言うより、それくらいしか方法がなく、やむなくやっていたのである。それを、視聴者がもっと主体的に言えるような刺激を与える、テレビ的な方法がないだろうかというのである。 次の週に先生がスタジオに来るまでの1週間、いろいろに考えて、極めて単純、素朴にして、最もテレビ的な手法を思いついた。 それは、テロップのダブりだけでやってみようというのである。つまり、4つなら4つの状況を、漫画家の上田次郎さんに描いてもらい、それに矢印のテロップをダブらせる。そして、次々とテロップをカットで切り替えていくことにより、視聴者は、矢印が指し示すところを発話するのである。テロップを切り替える時、「ヒューポン」という効果音をつけると、まるで、今でいうCGのように、矢印が小気味よく飛ぶのである。 しかし、本番の日、これで本当に行けるのかどうか、はたして、この「ヒューポン」「ヒューポン」だけで、30分、番組が持つのだろうか、という心配で、リハーサルが終わるまでは、不安でたまらなかった。しかし、この単純にして素朴な手法が、むしろそれゆえに効果を上げ、その後「会話文型練習」シリーズとなったのである。このシリーズは、最初、昭和44年2月の1か月間放送した後、再放送を入れると、10シリーズ近く放送することになる、英会話番組としては、異例のシリーズとなったのである。 こうして、「会話文型練習」シリーズが、私の唯一の功績になった、と自慢したが、それは、使い回しのテロップだけで、10シリーズも持たせたという、予算的に多大な功績があったという意味である。 このように、田崎先生からは、番組作りの面白さや醍醐味を教えてもらった「英語会話初級」だったが、最後に、お詫びをしなければならないことがある。このリポートの冒頭で、「語学がからっきしダメ」と書いた。「英語会話初級」担当の2年間、最高の先生とゲストにお付き合いいだき、「会話文型練習」シリーズで、何回も練習しながら、今もって「からっきしダメ」のままなのである。これは、全面的に私の能力の問題であることを申し添える次第である。 |